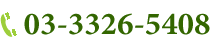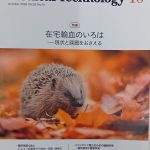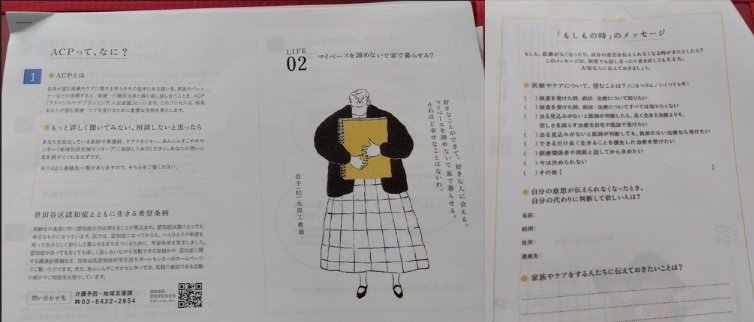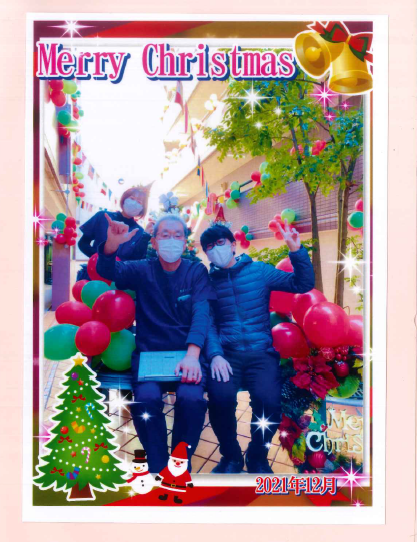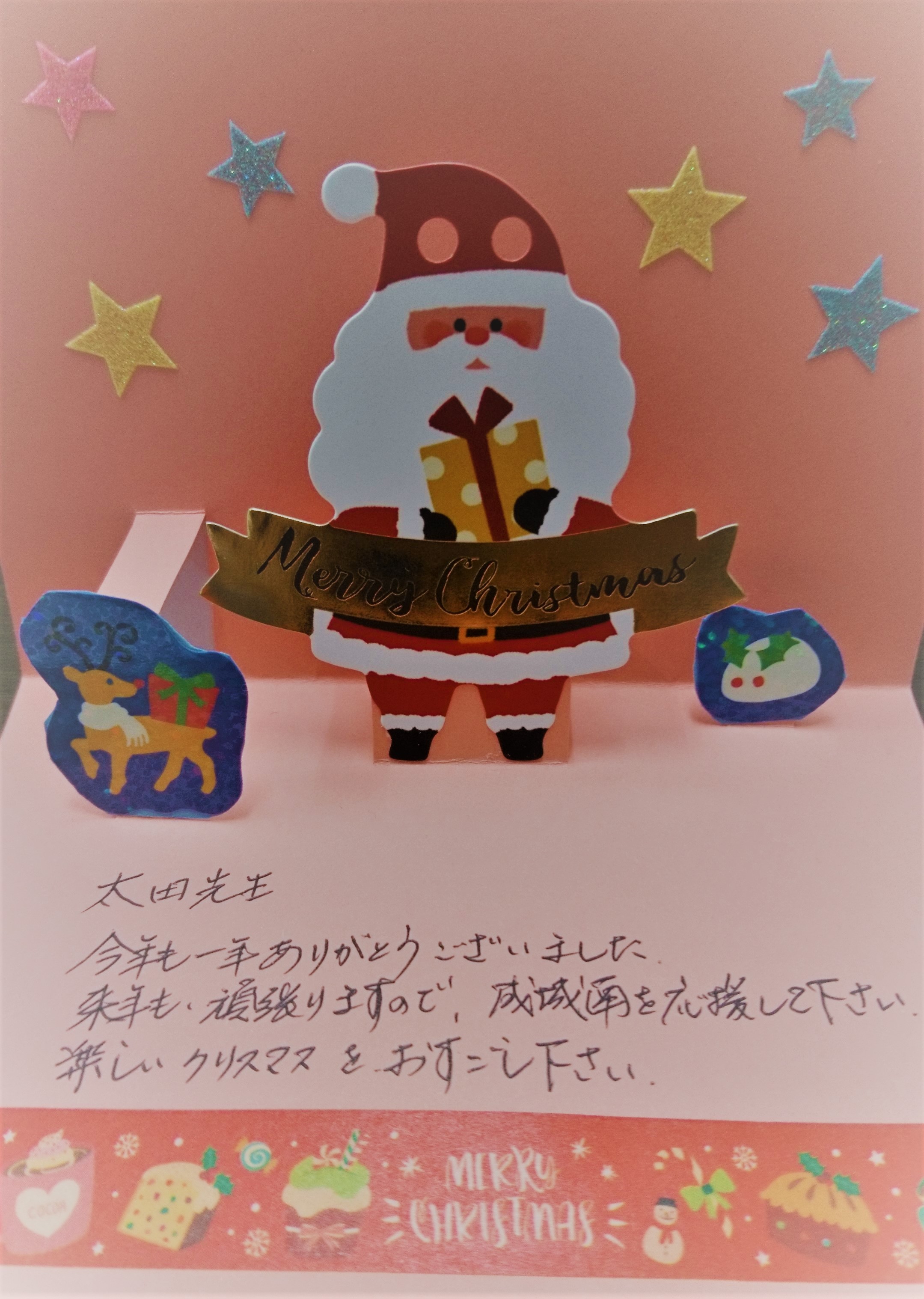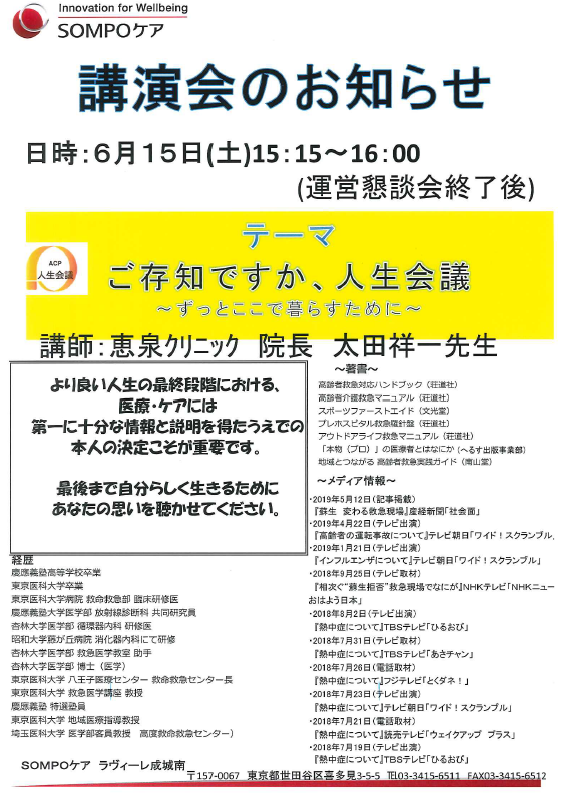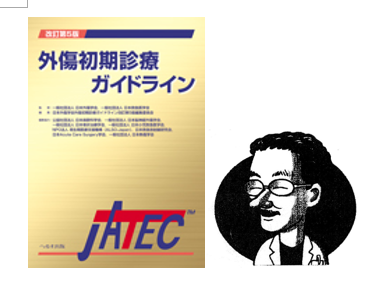当院では以前から積極的に取り組んできましたが、このたび「人生の最終段階における適切な意思決定支援にかかる指針」を作成し、ホームページで公開しました。
当院の指針は、ホームページ内「クリニックのご案内」に掲載しています。
【参 考】
人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドラインについて、以下から抜粋、解説します。
Microsoft Word – 03:【最終版】ガイドライン解説編 (mhlw.go.jp)
(人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン 解説編)
Microsoft Word – 02:【最終版】ガイドライン (mhlw.go.jp)
(人生の最終段階における医療・ケアの 決定プロセスに関するガイドライン)
このガイドラインの流れ
平成19年に終末期医療の決定プロセスに関するガイドラインが作成されました。このころは人生の最終段階における治療の開始・不開始及び中止等の医療のあり方が社会問題となり、医療のあり方についてのガイドラインが作成されました。
その後、平成27年には、「終末期医療に関する意識調査等検討会」で、最期まで本人の生き方(=人生)を尊重し、医療・ケアの提供について検討することが重要である、という観点から、検討会の名称も「終末期医療」から「人生の最終段階における医療」へ変更されました。平成30年には、高齢、多死社会の進行に伴う在宅や施設における療養や看取りの需要が増えたことを背景に、地域包括 ケアシステムの構築も進められていること、また、欧米で進められているACP(アドバンス・ケア・プランニング:人生の最終段階の医療・ケアについて、本人が 家族等や医療・ケアチームと事前に繰り返し話し合うプロセス)の概念を盛り込み、医療・ 介護の現場での普及を目的に「人生の最終段階における医療の普及・啓発 に関する検討会」において改訂され、このガイドラインは、人生の最終段階を迎えた本人・家族等と医師をはじめとする医療・介護従事者が、最善の医療・ケアを作り上げるプロセスを示していることから、 医療だけでなく介護、ケアが含まれるようになりました。
【基本的な考え方】
1)人生の最終段階では医療・ケアチームで本人・家族等を支える体制を作ることが、重要です。
2)できる限り早くから肉体的な苦痛等 を緩和するためのケアが行われることが重要です。緩和が十分に行われた上で、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケアの内容の変更、医療・ケア行為の中止等について、本人の意思を確認することがもっとも重要です。この確認では、適切な情報に基づく本人による意思決定 (インフォームド・コンセント)が大切です。
3)医療・ケアチームは、本人の意思を尊重するため、本人のこれまでの人生観や価値観、どのような生き方を望むかを含め、できる限り把握することが必要です。また、本人の意思は変化する、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性がある、ことから、本人が家族等の信頼できる者を含めて話し合いが繰り返し行われることが重要です。
4)本人の意思が明確でない場合には、家族等の役割が重要です。特に、 本人が自らの意思を伝えられない状態になった場合に備えて、特定の家族等を自らの 意思を推定する者として前もって定めている場合は、その方から十分な情報を得たうえで、本人が何を望むか、本人にとって何が最善かを、医療・ケアチームで話 し合う必要があります。
5)本人、家族等、医療・ケアチームが合意に至った内容は、それはその本人にとってもっとも良い人生の最終段階における医療・ケアだと考えられます。医療・ケアチームは、合意 に基づく医療・ケアを実施しつつも、合意の根拠となった事実や状態の変化に応じて、柔軟な姿勢で人生の最終段階における医療・ケアを継続すべきです。
6)本人、家族等、医療・ケアチームの間で、話し合いを繰り返し行った場合においても、 合意に至らない場合には、複数の専門家からなる話し合いの場を設置し、その助言により医療・ケアのあり方を見直し、合意形成に努めることが必要です。
7)このプロセスにおいて、話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくことが必要です。